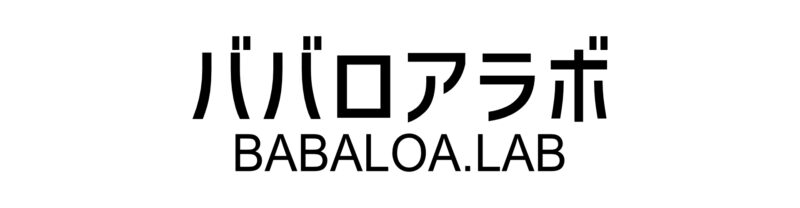こんにちは、ババロアです!塾講師・教員歴10年以上。特別支援学級担任から学年主任まで、さまざまなポジションを経験してきました。

あなたのクラスに学級文庫がありますか?
学級経営を行う上で、とても効果的な学級文庫。
教室に本を置くことで、クラスに良い影響を与えます。
学級文庫を置くことのメリットは大きく、学級経営において良いツールとなります。
»学級文庫は良いクラス作りに必要です!クラスを活性化させる書籍たち
とはいえ、
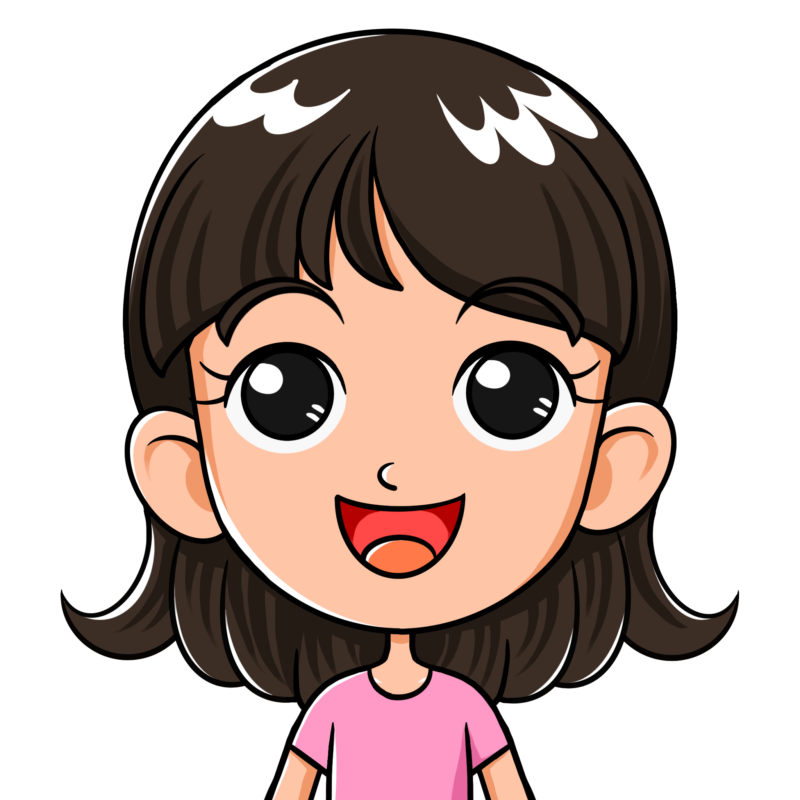
先生!学級文庫ほしい!!

いいけど…何を置けばいいかわからない!!!
と悩んでしまうことも。
ということで、本記事では学級文庫(学級図書)におすすめの書籍を紹介していきたいと思います。
学級文庫の種類に悩む先生方はぜひ参考にしてください。
中学生におすすめの学級文庫(学級図書)
中学生におすすめの学級文庫を10冊紹介します。

とりあえず何を置けばいいんだろう?
と考えている先生はぜひ参考にしていください。
カラフル
前世で大きな過ちを犯して死んでしまった「ぼく」。
本来であれば輪廻から外される罪な魂であるが、抽選に当たり小林真としてこの世にホームステイする事になる。この本はそんな所から始まります。
この本は自分を「客観視」して見る事の大切さ教えてくれます。
ぼく=真であり、実は同一人物です。しかし、真よりぼくの方が周りとの人間関係が良いのです。
それは何故か?それは肩の力を抜き正しく「客観視する力」を持って周りの人と関わったからだと思います。真は周りの人に期待を寄せて裏切られ続けたのでしょう。
一方、ぼくは真ではないと思い行動しているので周りの人達の良い所も見る事が出来る心の余裕が有ったのではないかと思います。
「きれいな色もみにくい色も。角度次第ではどんな色だって見えてくる」
この本の中で一番大好きなフレーズです。そしてこの物語の全てを物語っていると思い胸が熱くなりました。
君たちはどう生きるか
80年以上前に書かれた作品であるにも関わらず、現代の若者たちの心を打った作品です。
舞台は昭和初期。中学2年生の主人公である「コペル君」と「叔父さん」がノートを通じてやりとりをしていきます。
「コペル君」は早くに父を亡くし母子家庭で育っていますが、この「叔父さん」の存在があり良かった、と思わずにはいられないほど、心が温まるやりとりがなされていきます。
「叔父さん」の素晴らしいところは、「コペル君」にヒントは与えつつも、すべてを教えるわけではないというところです。
「コペル君」が自分で考え、自分で行動できるように促している。とは言っても、冷たく突き放すこともしない、ほどよい距離感でのやりとりに、心が温まります。
「生きていく上で大切なことは、時代を超えても変わらない」
今を生きる中学生に、そんなことを教えてくれる一冊です。
星の王子さま
読むとじんわりと癒やされる。しかし、どこかそこはかとなく悲しい…。そんな物語です。
主人公の王子さまは、いくつもの星をめぐり、7人の大人と出会います。
王子さまは、自由で純粋でまっすぐだからこそ、発言のひとつひとつに心をぎゅっと掴まれるような感覚になります。
愛らしい言葉の裏側には、何通りもの解釈が隠れているように感じることも。
そんな彼だからこそ、描くことの出来た物語。多感な時期の中学生におすすめの書籍です。
君の膵臓をたべたい
2017年に実写映画化、2018年アニメ映画化された「キミスイ」の原作の小説です。
主人公の僕が、病院で拾った日記を読み、クラスメイトの山内桜良が、膵臓の病気で余命が短いことを知ります。人に興味のない僕が、桜良と一緒に行動していくうちに、次第に考え方が変化していくという話です。
テンポよくストーリーが進むので、読みやすい本です。あちこちに伏線が散りばめられていて、最後に仕掛けがわかるようになっています。
10代の瑞々しい感性から出る繊細なセリフと、予想を裏切る展開に、心が揺さぶられる一冊です
夢をかなえるゾウ
夢をなくしたサラリーマンのもとに、関西弁のへんてこなゾウが現れた?!
笑いあり涙あり(?)な小説型自己啓発書です。
「自己啓発書」と聞くと身構えてしまう人もいると思いますが、本書は小説型ということもあり、読みやすく、抵抗感が少なく読める一冊です。
著者の水野敬也氏も、”読者が「自分でもすぐ実践できそう」と思えるハードルの低い実用書を書こうと思った”のがきっかけだったと話しています。
ゾウから出される課題を、読者も主人公と共に取り組んでいく部分も、この本の特徴です。「なぜこの課題をやるのか」という説明もゾウからされていて、中学生にもわかりやすい内容となります。
たとえば、「ただで何かをもらう」という課題がありますが、これは「人から助けてもらう人たちには、そうされるだけの理由がある。それを意識していたら、言い方や仕草ひとつにとっても気を遣うようになる」という理由が説明されています。
「稼ぐため」「成功するため」という目的で課題は出されていますが、「より良く生きる」「人生を豊かにする」という目的も達成できる課題でもあると感じました。
自己啓発本に馴染みのない中学生にも、読みやすく実践しやすく一冊です。
13歳から分かる! 7つの習慣 自分を変えるレッスン
この本は『7つの習慣』という本から重要なエッセンスを抽出し、読みやすくまとめられたものになっています。
そして、ストーリーが展開されているので、主人公と一緒に「7 つの習慣」を学んでいくことができました。
とても実用的な内容だったので、すぐに実践できます。また、多くの自己啓発本などと共通していることが多かった印象です。
まさに、自己啓発本の集大成とも言える一冊でした。この本は、うまくいかないことが多いという方や人生を充実させたいという方におすすめです。
普段読書をしない方も、この本ならすらすらと内容を理解できると思います。今後、何回も読み返したいと思うほど素晴らしい本でした。
西の魔女が死んだ
中学一年生の「まい」が、魔女と一緒に暮らしたひと月あまりの物語です。
都会の喧噪から離れた静かな土地で、彩り豊かな毎日を送る様子は、読んでいて心が透き通っていくような感覚になる。美しい自然の描写は、文字から情景が浮かび上がってくるようでした。
主人公の「まい」は中学校での人間関係に悩んでいたが、同じような悩みを抱えている十代の女の子はたくさんいるのではないかと思います。
「自分で決める」ことの大切さ、尊さを知ることで、人は誰だって今より強くなれるのかもしれません。
人間関係に悩んでいる中学生にこそ読んでほしい一冊です。
そして誰もいなくなった
たとえ結末が分かっていても、「あの場面で誰が誰を疑っていたのだろう。誰を信じ、何を感じていたのだろう」と思わず振り返りたくなるシーンが、多く存在する。
人間の猜疑心や思い込み、罪悪感といった生々しい部分が、さまざまな角度から描かれている。
「犯罪行為を行ったわけではないが、罪の意識を感じている」といった経験は、誰にでもあるのかもしれないと気づかせてくれる作品でもある。
きみの友だち
「みんな」って誰だろう。「親友」って何だろう。「友だち」ってたくさんいた方がさびしくないの?
そんな簡単に答えが見つからないようなことを、子どもたちの学校生活を通して考えていきます。読んでいて、胸の奥がぎゅっとつかまれるような、そんな話がいくつもあります。
連作短編集であるため、同じ登場人物が、違う話で何度も登場します。
登場人物に愛着がわきやすいような作りになっていると感じました。話の主人公のことを「きみ」と作者が記しているところも、非常に温かみがある作品です。
ミライの授業
というフランシス・ベーコンの言葉を体現したかのような一冊です。
歴史上の偉人エピソードが多く紹介されています。
特徴的なのは、成功談ばかりがまとめられているわけではないというところ。誰もが知るような人物の、失敗談や教訓になるようなエピソードも紹介されています。
「14歳のきみたちへ」という見出しから始まる通り、中学生の読者を想定して作られた書籍です。しかし、著者は「かつて14歳だった大人たち」にもこの本を贈りたいと本書の終わりで述べています。大人が読んでも学びが多い一冊であることには、間違いないでしょう。
学級文庫をそろえて、クラスを良い雰囲気に!
今回紹介した本を学級に置いておけば、クラスの雰囲気が良くなること間違いありません。
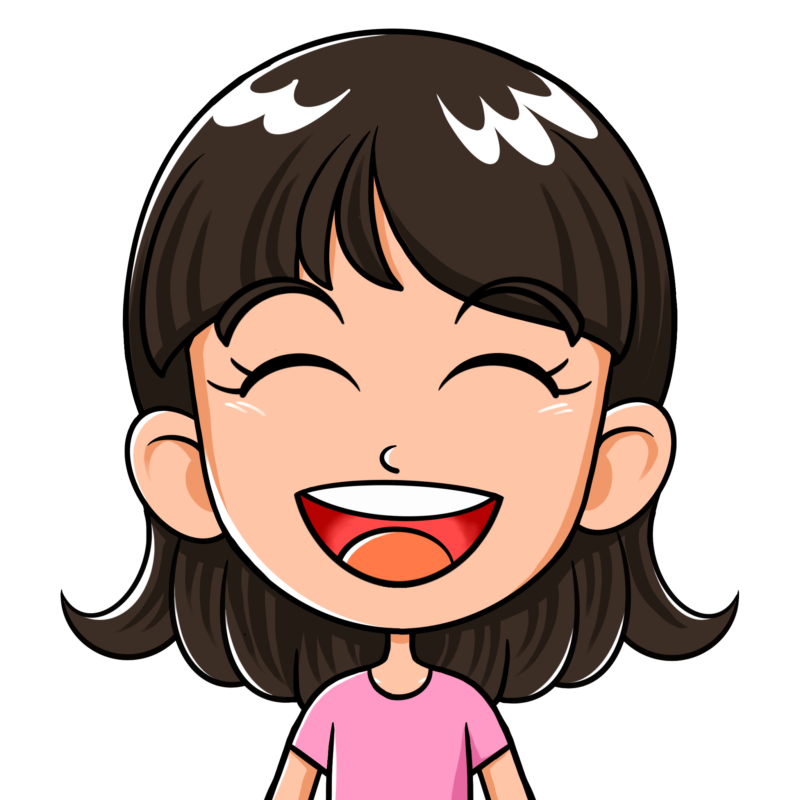
聞いたことあるけど、読んだことない本がたくさん!

定番ですが、とても良い本ばかりです!
学級文庫を適切に選ぶこととで、クラスの雰囲気は良くなっていきます。
そのためにも、学級通信のメリットを理解しつつ、学級文庫を学級経営に生かしていきましょう!

Twitterでも情報発信中!

Twitterでも、
先生を応援する情報発信中!
・ブログのお知らせ
・最新の教育情報にもリアルタイムで発信
・何気ない、けど面白いツイートも…
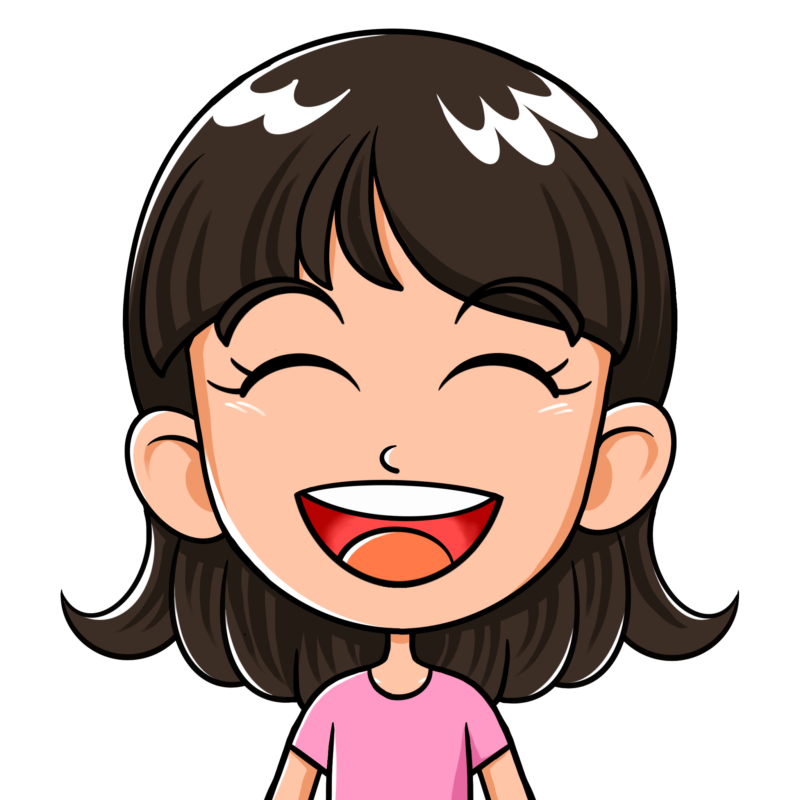
ブログとはまた違った発信が楽しめるかも!

Twitterのフォローお待ちしております!