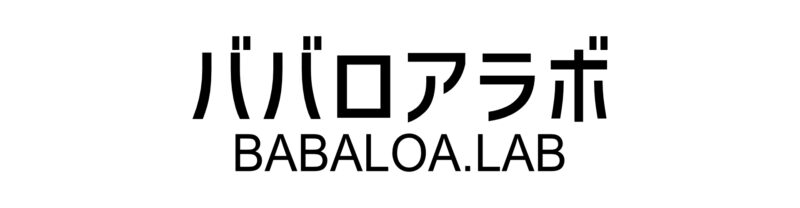こんにちは、ババロアです!塾講師・教員歴10年以上。特別支援学級担任から学年主任まで、さまざまなポジションを経験してきました。
学級崩壊を引き起こしやすい先生の特徴を知り、ステキな学級を作っていきましょう!担任をしていて一番こわいのが「学級崩壊」です。
「学級崩壊だけは防ごう」と思っても、知らず知らずのうちに崩壊してしまうこともあります。
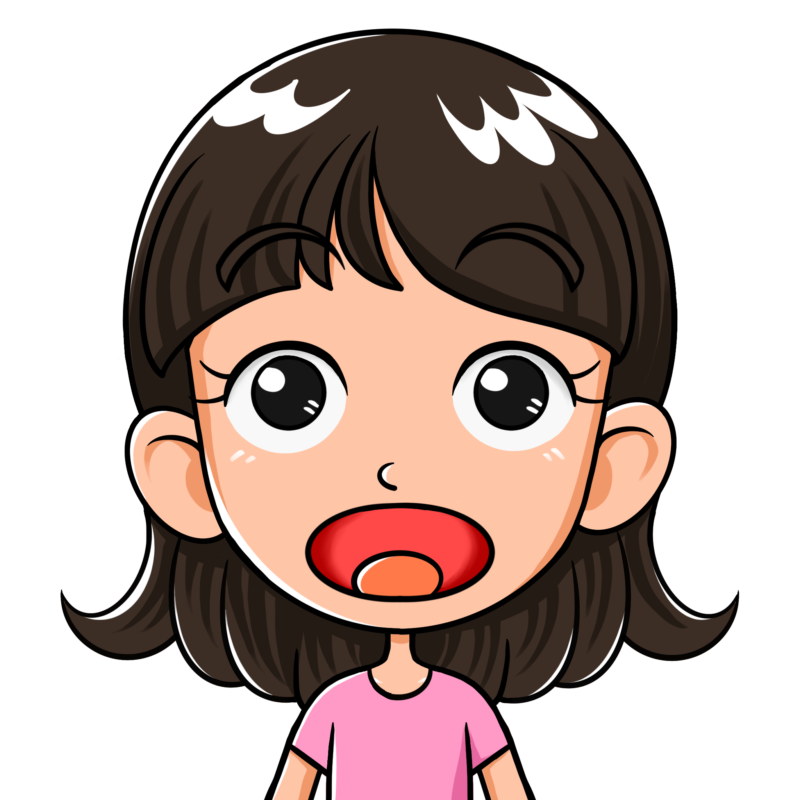
え!?うちのクラスも崩壊する可能性あるの!?

どんなクラスでも可能性あり!
特に、
・伝わっているようで、伝わっていない話
・管理的な学級経営
学級担任がこれらを意識しないと、学級は崩れ始めます。
ということで、本記事では「学級崩壊を引き起こしてしまう先生の特徴と対策」を深掘りしていきたいと思います。
学級崩壊を引き起こしやすい先生の特徴
学級崩壊が起きやすい先生の特徴として、
・伝わっているようで、伝わっていない話が多い
・管理的な学級経営をしてしまっている
が考えられます。

私のクラス、担任の先生の話を聞いていないかも…

1つでも当てはまれば、学級崩壊の危険性があります。
学級崩壊の兆候を見逃さず、対策をしていきましょう。
»対策と改善を考える!学級崩壊を立て直すために意識すべきこと3選
担任と子どもの立ち位置
学級経営をしていると、

子供との関係性が難しい。
と感じることはありませんか?
むしろ、これを感じない先生は学級崩壊の危険性がアップします。
・子どもたちと同じ言葉づかいになっていないか
・子どもたちと関わっているときの自分の姿はどのようなものか
これらを定期的に見直すことをオススメします。

ほど良い距離感が大切です。

たしかに、先生が近づきすぎると避けてしまう。
「あの先生ならどんな悪口を言っても大丈夫」や「あの先生なら何を言っても意味がない」と子供と先生の信頼関係が崩れてしまうことも。
これが学級崩壊の原因につながります。
また、今ではSNSで子供と先生が繋がってしまうこともあります。

これはメチャクチャ危険です。
SNSやLINEでつながることで、先生という立場が薄れてしまい、学級経営に影響を及ぼしかねません。
»先生と生徒がLINEを交換する世の中に!?子どもと教員はSNSでつながるべきかを考えましょう
友達ではなく「先生」という立場を理解して、適切な距離感で子供と接するようにしましょう。
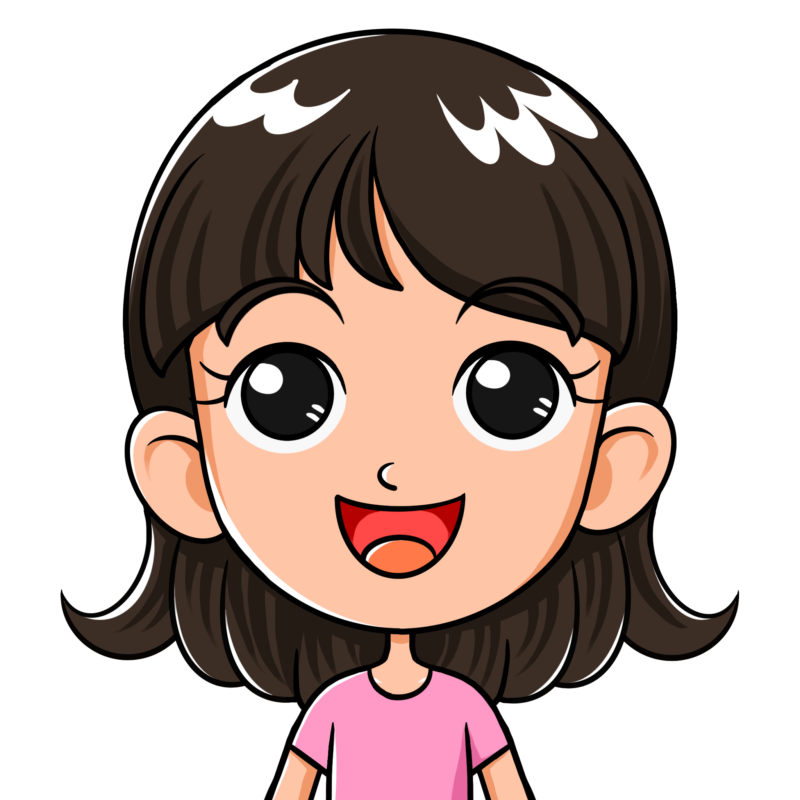
近すぎず、遠すぎない関係が良いんだね!

そうそう!
助けてくれるし、見捨てられない。そんな関係でありたいですね。
ついつい距離感を間違ってしまうこともありますが、その都度見直して、良い関係性を作るようにしていきましょう。
先生の話は、伝わっているようで伝わっていない
「先生からの話なんだから、しっかり聞いているだろう」と思っていても、実はほとんど伝わっていません!

先生の話って覚えてる?

いや、あんまり覚えていない…
どれだけ伝えようとしても、なかなか伝わらないものです。
とはいえ、伝えるための工夫はいくらでも可能です。
・自分の考えを押し付けていないか
上記2点を意識するだけでも、かなり伝わりやすくなります。

声の大きさを意識してみると、大きすぎてびっくりします。
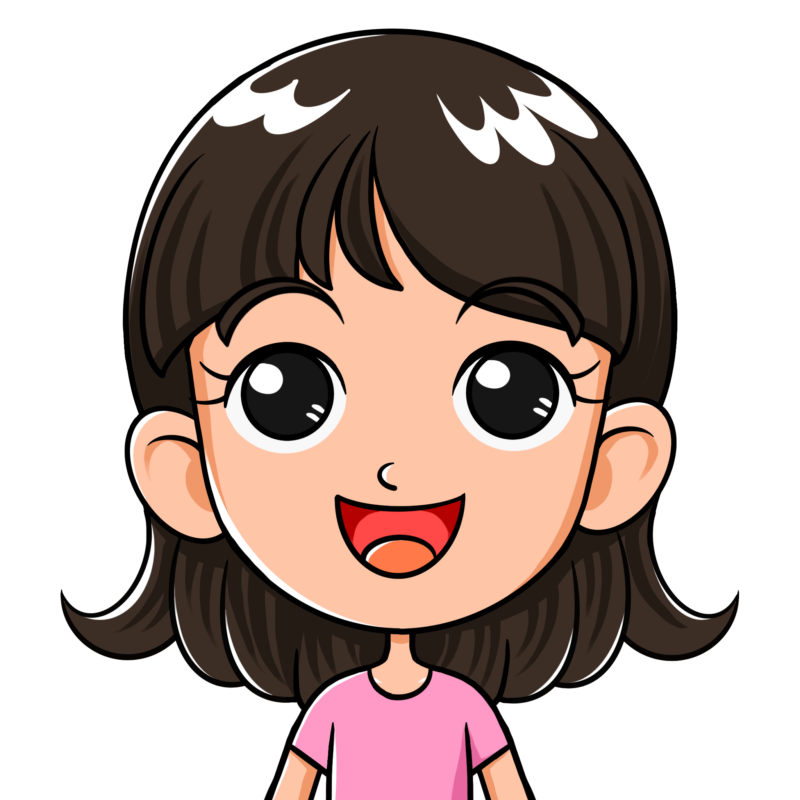
私の担任の先生も声が大きい!
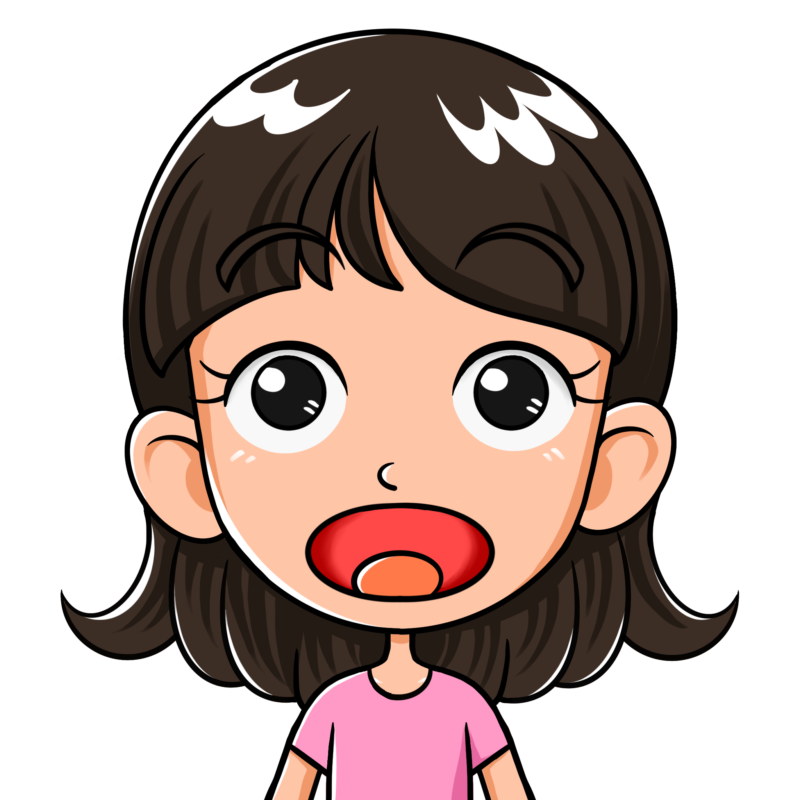
大きすぎて、聞き取りにくいことも…
実はあえて「ボリュームを下げる」ことも伝えるテクニックの1つです。
また「話し方」の工夫次第で子どもの行動が変化します。

言葉かけ1つでクラスが変わります。
「伝え方コミュニケーション検定」といった実践的な技術を学ぶことで、クラスに良い影響を与えることもあります。
「伝える」「伝わる」というところを意識して、学級の子どもたちを良い方向に導いていきましょう。
メリットの少ない管理的な学級運営

管理されるのは、大人でも嫌です!子どもを管理しようとせず、一緒に学級を作りましょう!
子どもを管理しようとすればするほど、子どもたちは離れていってしまい、学級崩壊につながってしまいます。
・なぜ注意しているのか、理由が明確でない注意をする
・高圧的な姿勢で行動を制限する
・学級担任が主体となった学級づくり
上記が管理的な学級運営の代表的な例です。
つまり、子どもたちのマイナス面が浮きだってくる学級経営が、学級崩壊の火種となってしまうのです。

正直、学級経営において「先生と子どもの上下関係」を作って、高圧的に指導を続けていくのは簡単です。しかし、子どもの心は育たず、いつ崩壊してもおかしくない学級づくりになってしまいます。
管理ではなく、良い人間関係のサイクルを築く
子どもたちを管理するのではなく、先生という立場から「ステキな人間関係」が作れるようにしてあげましょう。
上記のようなサイクルができてくると、たくさんの人間関係が形成されていきます。
なかには人間関係が苦手な子もいますが、もし子ども同士でのつながりが難しい場合は、先生がその1人になってあげてください!
人間関係の好循環サイクルについては組織や人間関係において、良い関係性を構築するためのサイクル
を参考にして下さい。

ビジネス向けの記事ですが、「組織」を「学級」に置き換えて読んでいただけると、学級経営における人間関係の作り方の参考になります。
「学級は、子どもと教師がともに居場所を作る場所」ということを頭に入れて、「みんなが安心できる学級づくり」を目指してください。
学級崩壊をさせないための取り組みをすすめましょう

学級が崩壊するのが怖すぎて、たくさんの取り組みをしてきました。具体的な取り組みを紹介します!
私が現役教員時代に取り組んでいた学級経営を紹介します!
学級通信で「思い」の共有
「学級の子どもたちと自分の思いを共有する」という目的のもと、学級通信を書きまくっていました。
・担任として抱いている思い
・研修で学んだことや、ニュースを聞いて感じたこと
主には上記の3点を学級通信のネタとして発行していました。

年間100号くらい発行していたのですが、正直疲れます!笑
年間100号出そうと思うと、負担感がグッと上がります。

子どもたちに伝えるために、あらゆるアンテナを張らなければならないので…。
しかし、学級通信は学級経営において大きな効果を発揮してくれます!
子どもたちとの信頼関係だけでなく、保護者とも思いを共有できるので、学級に対するクレームもほぼほぼありませんでした。
学級の子どもや保護者と思いが共有できる学級通信を生かすことで、気持ちのギャップから生まれる学級崩壊を防ぐことが可能になります。
また、学級崩壊の予兆(子どもたちの言葉遣い・人と接する時の態度)があった場合は、すぐに学級通信を書き始めましょう。

年度途中からでも全然OKです。「最近の学級をこんな風に見てるんだよ」と先生の思いを伝えてあげて下さい。


インクルーシブ教育で、「安心感」のある学級づくり
安心感のある学級づくりとして、インクルーシブ教育に取り組むのも効果的です。
「自分の居場所のないクラスは嫌いだ」と感じる子どもが一人でも出てくると、その思いは伝染して、学級崩壊につながってしまいます。
インクルーシブ教育とは本来、「障がいの有無に関わらず、あらゆる子どもが共に学ぶ」ことを目的としています。
つまり「多様性を受け入れて、同じ空間で生活をする」ということです。

多様性を受け入れられる雰囲気づくりをしっかりと行い、子どもたちに「安心感」を感じさせてあげてください。
インクルーシブ教育について詳しく知りたい方はインクルーシブ教育の意味と合理的配慮について【居心地の良い学校づくり】を参考にして下さい。

うまくいかないことも多々あると思いますが、じっくりと学級をステキな空間にしていってください。きっとその思いが学級に伝わり、学級が崩壊することはなくなっていきますよ!!