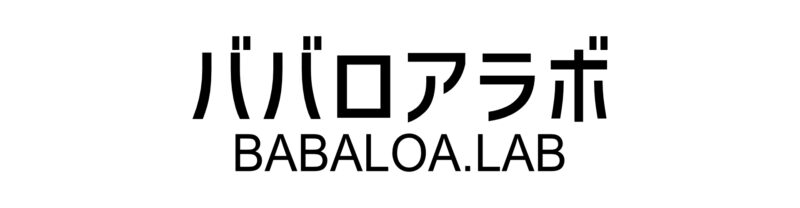こんにちは、ババロアです!塾講師・教員歴10年以上。特別支援学級担任から学年主任まで、さまざまなポジションを経験してきました。
自分の授業スタイルが確立するまでは「授業が上手くなりたい」という強い思いを持ちながら「わかりやすい授業」を展開するための研究をしてきましたが、ある時気づいたことがあります。
その答えが先日のツイートです。
授業は間(ま)が大切。
間が悪いと子どもたちの興味が逸れて授業の質が悪くなり、間が良いと授業が活き活きしてくる。
ベテランと新任の決定的な違いは間の作り方かもしれない。— ババロア@フォロワー1000人目指す教育ブロガー (@blogger_study) 2019年4月23日
教科についての知識をつけることや、授業の引き出しをたくさん作ることも、もちろん大切なことです。
しかし、「間の大切さ」を意識して授業をしなければ、授業の良さは生きていきません。
本記事では「わかりやすい授業に存在する間」について深堀りして解説していきたいと思います。
間を意識することで、授業がわかりやすい先生になれます

「一生懸命、教材研究をしているのに一向に授業が上手くならない」「何度授業をしても、子どもの理解が進まない」という悩みを持っている方はいませんか?
「わかりやすい授業」を展開するために、教員自身が知識をつけ、それを子どもたちに伝えようとする先生は多くいます。
しかし、教科に対する専門的知識をつけたり授業改善だけでは、子どもたちの理解は深まりません。
いくら素晴らしい授業をしたとしても「伝え方」を身に付けないことには、授業の理解度は上がりません。
授業がわかりやすい先生は「伝え方」を意識しています
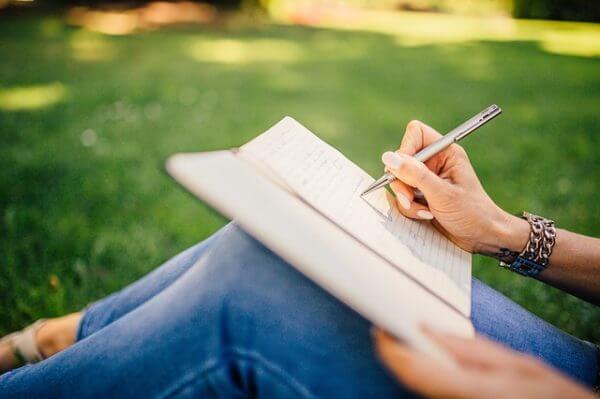
授業の理解度を向上させる上で大切にすべきことを下にまとめました。
・「活動」の間を考える
・「教員」としての余白を作る
以上の3つのを意識することで、授業の質が大きく変わります。
経験を積むことで自然と身につく場合もありますが、意識ひとつで「わかりやすい授業」に近づくことが可能です。
「子供主体」の授業を考える
授業は「聞き手」である子供がいなければ成立しません。
もちろん「話し手」である授業者も大切ですが、あくまで主役は子供たちです。

子供を意識していない授業は「教員の自己満足」ともいえるでしょう。
授業者は、聞き手である子供たちを意識して、授業展開を考えなければなりません。
授業展開を考えるとき「子供たちは授業展開を知らない」ということを意識してください。
授業展開を知っている先生は、「早く話してしまいたい」という気持ちを持ってしまいがちですが、子供たちはそうではありません。

要所要所で考える時間を作って、聞き手が理解する時間を作ってあげましょう。
教員主体の授業になってしまうと、子供が理解する前に授業が進んでしまいます。
知識を伝えた後に、知識を整理する時間を意図的に作ってあげましょう。
»授業導入のネタに困ったら!授業の展開からデザインするネタづくり
声量も大切
「声の音量」も意識することができれば、より子どもを引き付けることができます。
「教員ならば大きな声で!!」という先生もいますが、声を大きくしたところで逆効果です!!
本当に子どもたちに伝えたいならば、声のトーンやスピードを意識して話しましょう。
子供たちが騒がしい時こそ、小さな声でゆっくりと話すことで、子供の注意を引くことができます。
声のトーンやスピードをコントロールできるようになると、大きな武器になるのでオススメです。

「活動」の間を考える
授業の中で、子どもたちは様々な活動を行います。
どの授業においても、この活動が主になってきますが、それぞれの活動で「間」を意識してください。
器用な子どもであれば、説明を聞きながら板書を書き写すことは可能でしょう。
しかし、そうでない子どもが多くいます。
説明を聞く・ノートを書くという活動が同時にできません。
授業者からすれば、説明を聞く・ノートを書くという活動を同時にしてくれた方が授業時間の短縮になり、効率良く感じます。

しかし、この考え方は授業者目線であり、子供のことを全く考えていません。
説明を聞く活動とノートを書く活動に「間」を作ることで、聞き手は説明を十分に聞くことができます。
また、
といった、インプットからアウトプットまでの活動が短時間でできるため、学習定着度も上がります。

授業の雰囲気を意図的に作る
一番習得が難しいのが、この「雰囲気づくり」です。
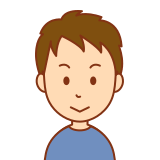
あの先生、授業以外では子どもから気さくに話しかけられているのに、授業になると子どもがキリっとする。なぜ??
授業とそれ以外の時間で、子どもからの関わり方が変わる先生は、「授業の雰囲気」を大切にしている先生です。
授業の「聞かせたい時間」になると、子どもたちが「聞かなければ」という雰囲気を作ります。
・子供が騒がしくなってきたら、落ち着くまでの余白を作る
・先生の話を一生懸命聞こうとしている子供に、ポジティブな声かけをする
理想とする先生の授業を見て、真似をしながら自分にあった「教員の余白の作り方」を見つけて下さい。
余裕をもって授業に臨みましょう
わかりやすい授業を実現するためには、余裕を持って授業準備をする必要があります。
・知識量が不足している
・子どもと関わる時間がない
このような状況では「わかりやすい授業」を作り出すのは不可能です。
授業準備が満足にできるよう、仕事の生産性を上げたり、同僚とノウハウを共有するなどを行ってください。
「わかりやすい授業」は誰でもできる

私自身も教材研究を熱心にし、知識を詰め込んでいたにも関わらず、子どもに伝わらないと悩んだ時期がありました。
悩みに悩んだ私は、同じ授業内容をしていた同僚の授業を参観させてもらうことに。
正直「自分の方が面白い授業をしている」という自負がありましたが(調子にのっていました)、授業を見て本当に驚きました。
・伝わりやすい言葉選び
これらを上手くデザインしていたのです。
教員として「わかりやすい授業」を作ることは、大切な大切な仕事です。
目の前の子供の学力を向上させ、より良い人生を作れるよう、今回お話ししたポイントを意識した授業づくりを楽しんでください。
Twitterでも情報発信中!

Twitterでも、
先生を応援する情報発信中!
・ブログのお知らせ
・最新の教育情報にもリアルタイムで発信
・何気ない、けど面白いツイートも…
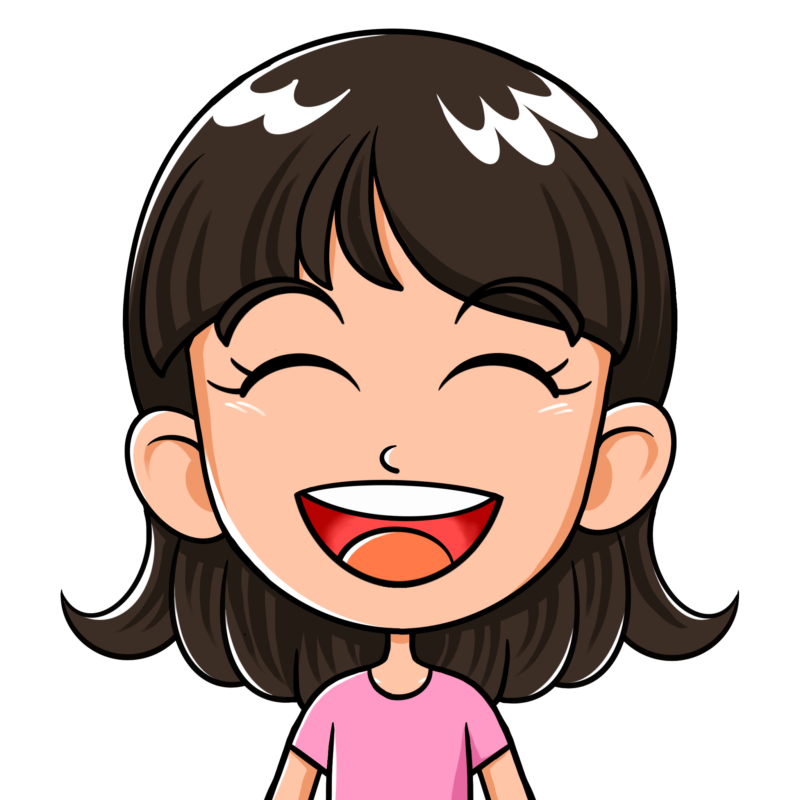
ブログとはまた違った発信が楽しめるかも!

Twitterのフォローお待ちしております!