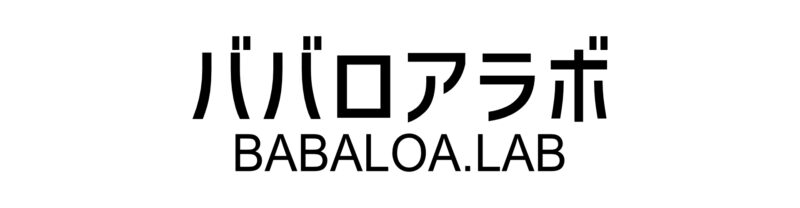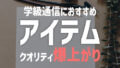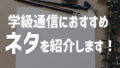こんにちは、ババロアです!塾講師・教員歴10年以上。特別支援学級担任から学年主任まで、さまざまなポジションを経験してきました。
学校の先生って無限に働いているイメージありませんか?
なんなら、どんな時も学校にいて、「学校に住んでいるんじゃないか?」という先生もいます。
しかーし!実際には教員の残業時間は45時間までと決められています!!
本記事では、

・教員っていつまで残業しているの?
・残業の規則は守られているの?
・どうすれば残業が減るの?
このような悩みについて、以下のポイントで解説していきたいと思います。
・教員の残業の実態を解説
・教員の残業を45時間までに抑えるためには
学年主任や学級担任として学校で働きながら、月の残業時間を10時間程度に抑えることができた私が、教員の残業について徹底的に解説していきたいと思います。
教員の残業は45時間まで
教員の残業時間(超過勤務)の上限は45時間までとガイドラインにて定められています。
このガイドラインが出された趣旨は、
限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授業改善や児童生徒等に接する時間を十分確保し、教師が自らの授業を磨くとともにその人間性や創造性を高め、児童生徒等に対して効果的な教育活動を持続的に行うことをできる状況を作り出すことを目指して進められている「学校における働き方改革」の総合的な方策の一環として制定するもの。
つまり「勤務時間の中でしっかりと働いていこう」ということを述べています。

時間は無限じゃないからね!
学校現場では「時間・生産性・効率」をあまり意識せずに働く風潮がありました。
そのため、「長時間働いている先生=熱心」と考える人も多く、仕事が積もり積もっている状態が続いています。
特に部活動に力を入れる先生なんかは、勤務時間をオーバーして活動し、それに伴って他の教員もプライベートや家族を蔑ろにした働き方を強いられています。
»【勤務時間無視】部活動は教員の負担となっているのか【先生忙殺】
このような現状を改善すべく出されたのが、先ほどのガイドラインです。
ガイドラインによって定められている超過勤務の時間は、
・1か月の在校等時間について、超過勤務45時間以内
・1年間の在校等時間について、超過勤務360時間以内
このような基準を定められています。
1ヶ月の超過勤務の上限は45時間で、年間360時間以内に抑えるように示されているのです。
教員の残業の実態を解説
では、実際に「ガイドライン通りの働き方ができるのか」を解説していきます。
まずは上記の超過勤務の時間について、もう少し詳しくみていきましょう!
土曜日と日曜日による休みが月8回・祝日による休みが1回と仮定して、1ヶ月の勤務日数を22日とします。
勤務日数22日で残業時間の上限が45時間とすると、
45時間÷22日=2.04時間
となります。
つまり、1日の超過勤務の時間は2時間に抑えなければなりません。
また、年間360時間という上限で考えると、月の超過勤務の時間は30時間に抑える必要があります。
ということは、
30時間÷22日=1.36時間
というように、1日の残業時間を1時間ちょっとにしなければなりません。

そんなことできるの!?
現在、過労死ライン(超過勤務80時間)を超える教員は、中学校において6割近くいると言われています。
部活動が勤務時間を圧迫し、授業準備もままならない状況があるのも事実です。
»【ブラック公務員】教員の勤務時間を「法律」と「現実」で解説
そんな中で、このガイドライン通りの働き方を実現するのはかなり困難といえるでしょう。
しかし、このガイドラインのように超過勤務の上限が定められないことには、超過勤務を減らすなどといった動きは出てきません。
今後このガイドライン通りの働き方をするためにどう動いていくのか、国や各自治体の動きに注目していきましょう。
また、教員自身もガイドラインの中身を理解し、働き方改革に努めていかなければなりません!
教員の残業を45時間までに抑えるためには
ここからは残業時間を45時間に抑えるために、どうすれば良いかをみていきたいと思います。
部活動を地域の活動に
教員の超過勤務の一番の要因となっているのが「部活動」です。
»【勤務時間無視】部活動は教員の負担となっているのか【先生忙殺】
勤務時間を無視した時間設定から、多くの教員が超過勤務を強いられ、苦しめられています。
ちなみに、この超過勤務による手当てなどは無く、完全に教員による善意で運営されています。
この部活動を地域の活動にすれば、かなりの超過勤務を減らすことが可能です。

国が動いています!
2023年度から段階的に、
公立中高の休日の部活動を地域や民間団体に委託する
という改革案を国が発表しています!!
もちろん「休日」という限定的な改革のため、まだまだ不足している部分はあります。
しかし、将来的には「平日」の部活動についても地域移行を目指していくようです。
これについては、今後も国や各自治体の動きに注目していく必要がありますね!
授業準備の効率化
こちらは教員が個人(または学校全体)で行っていく必要があります。
「授業」は教員にとって、仕事の核であり、手を抜いてはいけない部分です。
しかしながら、1コマの授業に膨大な時間をかけていては、いくら時間があっても足りません。
では、どのように授業準備を効率していけば良いか…
1.他の先生と教材をシェアする
2.ICT機器の活用
まずは上記2つを進めていきましょう。
1.他の先生と教材をシェアする
共有フォルダなどを作成し、それぞれの先生が作った教材を溜めていきます。
そうすることで、教材がシェアすることが可能となり、自分で作る手間をかなり省くことが可能です。
また、教材をシェアする先生が増えたり、時間が経つにつれて、さまざまな教材が溜まっていきます。
年度が変わったり担当教員が変わったとしても、その教材を使うことができるため、教材が財産となっていくことでしょう。
2.ICT機器の活用
ICT機器をうまく使うことができれば、授業準備だけでなく授業の質がかなりアップします。
私自身、iPadをかなり活用し、授業準備の効率化を図っています。
教員の残業は45時間以内!?学校の働き方改革と実態について解説まとめ
本記事では、教員の残業に関するガイドラインについて詳しく解説していきました。

これから制度改革が起きる感じかな!
自由を手に入れる!教師が「独立・起業」するためのロードマップのように、教員を退職して起業を考えるのも1つの選択肢です。

自分の働き方を見直しつつ、持続可能な仕事にしていきましょう。
Twitterでも情報発信中!


Twitterでも、
先生を応援する情報発信中!
・ブログのお知らせ
・最新の教育情報にもリアルタイムで発信
・何気ない、けど面白いツイートも…

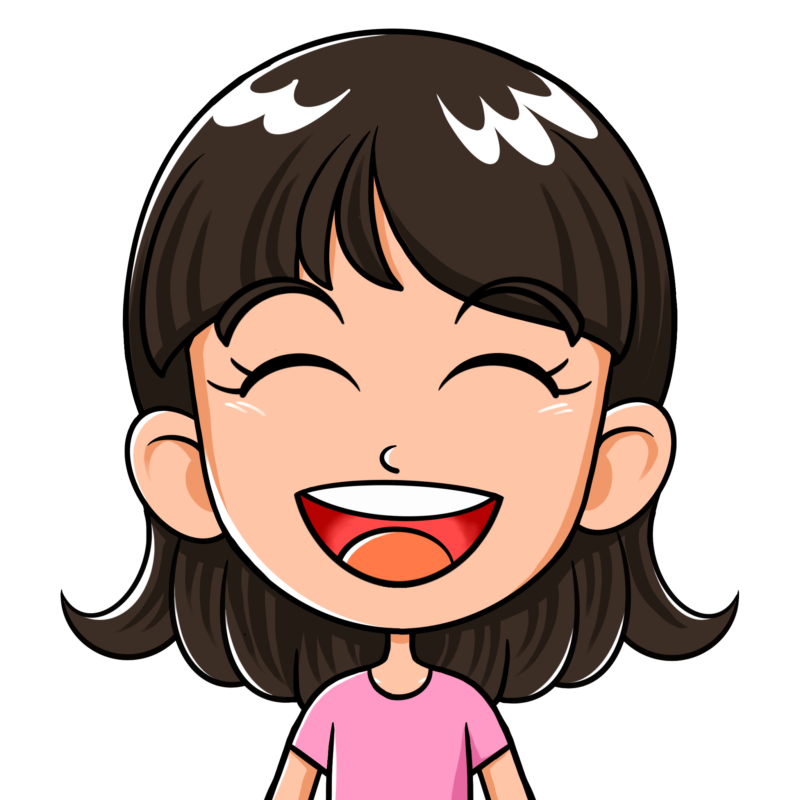
ブログとはまた違った発信が楽しめるかも!


Twitterのフォローお待ちしております!