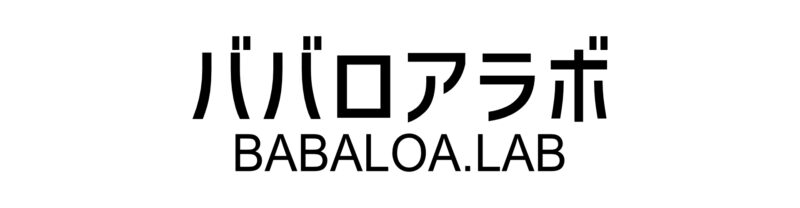こんにちは、ババロアです!塾講師・教員歴10年以上。特別支援学級担任から学年主任まで、さまざまなポジションを経験してきました。
先日、このようなツイートをしました。
学級担任してた時は「学級通信」をこだわっていました。
✅子供に価値観を共有する
✅クラスを客観的に見てフィードバック
✅保護者への情報共有
主に3つを意識することで、最強のアウトプットツールとなります。学級経営に悩んだら、通信を発行するのもアリですよ🐿✨— ババロア🐿先生の人生を豊かにする (@babaloa_lab) October 17, 2021
上記のツイートの通り、私は「学級通信」を1つの軸として学級経営を行っていました。

学級通信って効果あるの!?
学級通信を毎年約100号ちかく発行してきた私ですが、通信が浸透するまでは、よくこんな声を耳にしました。

手書きだったので余計に驚かれることも。
しかし、学級通信を発行するにつれてそんな声は次第になくなっていきます。

学級通信の効果は間違い!
本記事のポイントを理解して発行すれば、間違いなく効果が現れます。
ということで、本記事では年間100号発行する私が学級通信の作り方のポイントを徹底解説します。
ステキな学級通信の作り方まとめ
学級通信の作り方にはいくつかポイントがあります。
・内容の質を高める工夫をする
・馴染みやすいタイトルをつける
これらのポイントを意識することで、ステキな学級通信を作ることができます。

こんなにあるの!?

最初からカンペキじゃなくてもOKです!
4つのポイントはとっても大切ですが、すこしずつで大丈夫です。
ステキな学級通信が作れるように、徐々にポイントをマスターしていきましょう!
発行頻度を高める工夫をする
学級通信を生かすには、発行頻度を高める工夫が必要です。
発行頻度が低いと、

学級通信なんてあったっけ?
というような状態になることも。

これでは学級通信を発行する意味が薄れてしまいます。
学級通信を発行することで得られるメリットは、
・担任の価値観を定期的に伝えられる
・子どもだけでなく、保護者とも共有できる
・言葉だけでなく「文字」で伝えることができる
というように、学級経営をサポートするもがたくさん。
これらのメリットを得るためには、学級通信の発行頻度を高めることが大切です。
せっかく発行するのに、
・担任の負担が増えるだけ
これでは、せっかくの学級通信がムダになってしまいます。
発行頻度を高める工夫をして、学級通信を価値高めていきしていきましょう!
»【学級だより】発行頻度を爆上げさせる!学級通信におすすめのネタ
内容の質を高める工夫をする

発行部数を増やす工夫ができたら、通信の内容に意識を向けましょう。
内容の質が高まると、
・保護者が通信を楽しみにする
・発行すればするほど、通信の内容がクラスに浸透する
学級通信の効果がボディブローのように効いてきます。

次の通信はいつ!?
なんて声が聞こえ始めると最高ですね!
とはいえ、良いネタを見つけようとすればするほど困ってしまうことも。

今日は何を書こう…
そんな時は、普段の子供の様子に目を向けてみましょう。
子供たちの行動や言葉にアンテナを貼ることで、最高のネタがゲットできます。
ネタに困ったら以下のポイントを参考にしてみてください。
・授業の中で共有したいこと→授業内容だけでなくステキな発言なんかも
・休み時間の様子→遊んでいる様子や流行っていること
・行事→最高のネタです!複数号書くことも
・先生自身のこと→最近学んだことや、クラスを客観視した内容
このように、日常の中にネタはたくさんあります。
ポイントは先生の価値観を伝えることです。

先生ってそんなふうに見てるんだ!
と価値観を共有していくことで、クラスの意識が変わります。
»学級通信の質を高めるために「手書きの通信」をおすすめする理由
馴染みやすいタイトルをつける

よく分からないタイトルは危険!
タイトルをつけるときのポイントは馴染みやすいかどうかです。
「魑魅魍魎(ちみもうりょう)」などの口に出しにくいタイトルは絶対にやめておきましょう(さすがに魑魅魍魎はないと思いますが)。
「口に出しやすいタイトル」にする理由は以下の通りです。
・子どもが愛着をもつことができる
・書いている自分も愛着をもつことができる
気分的なものもありますが、口にしやすいタイトルをつけることで、「学級のキーワード」ができるのです。
私が学級通信のタイトルを決めるときの参考にするものを紹介します!
覚えやすくてインパクトのある言葉が見つかればいいですね!
学級の雰囲気にマッチしたワードを探してみましょう。
まずは書いて、それから考えましょう

「大変そうだしな~。」と悩んでる時間がもったいない!学級通信に興味があるなら、まずは書いてみましょう!!
学級通信を書こうか迷っている時間があるなら、まずは書き始めてみましょう。

いきなり書けるものなの!?
と感じてしまいがちですが、書きたいと思った時がタイミング!
私は学級経営の中に、学年通信を入れていました。
»手書きの学級通信をはじめたい!学級通信におすすめのアイテム
書けば書くほど、うまくなるので、まずは楽しみながら書いてください。
また、学級通信を書いた後も大切です。

配って終わりはもったいない!
配布した後のフォローを丁寧にすることで、学級通信の価値が爆上がりします。
せっかく書いた学級通信、大切な存在にしてください。
»学級通信の価値を高めるための工夫を紹介!通信を活用するためのヒント
今回紹介したポイントをおさえれば、学級通信がマイナスになることはありません。
本記事を参考にしつつ、学級通信を楽しんでください!
\手軽に文字上手になりたいなら/
Twitterでも情報発信中!

Twitterでも、
先生を応援する情報発信中!
・ブログのお知らせ
・最新の教育情報にもリアルタイムで発信
・何気ない、けど面白いツイートも…

ブログとはまた違った発信が楽しめるかも!

Twitterのフォローお待ちしております!